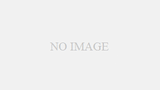あまりにも分かりやすいので採録
「間主観性」
人は、他人の感情を完全に客観的に理解する事はできません。「ああ、この人は悲しいのだな」とか、「なんだか、怒っているみたい」というのは、相手の表情やしぐさ、声のトーンなどから、表面的に判断しているのであって、あくまで分析による客観的推定です。この客観的推定の段階は、自我のレベルでなされるもので、相手の気持ちを十分に理解しているとは言えず、相手に対する共感も生じません。ここで、もう少し深いレベルで相手の気持ちを理解する場面について考えてみましょう。例えば、悲しい事があって、泣いている人がいるとします。あなたは、彼女の話を聞いて、とてもつらい気持ちになって、思わずもらい泣きをしてしまいます。なぜ、あなたは、泣いてしまったのでしょうか?この時、あなたは、あたかも彼女の悲しみが自分のもののように感じているでしょう。この「あたかも自分自身のもののように相手の気持ちを感じる」事が、共感です。共感は、けっして自我のレベルのみでは起こらず、もっと内面的な、自己と他者の境界線がなくなったようなレベルで起こります。このレベルでは、完全な客観性は存在せず、あなたは、相手の気持ちを主観的に理解しているのです。これは、あたかもふたりの主観が、ふたりの間をいったりきたりしているかのようです。こうした状態を間主観性と言い、間主観的な交わりが起こる領域を間主観的なレベルと言います。間主観的なレベルにおいては、完全に客観的な対象は存在せず、自己対象と呼ばれる自己の中の他人により、他者を主観的に理解しようとします。こうした他者を主観的に理解する共感により、その人は癒され、安心し、困難を克服したり、生きているという実感を取り戻したりします。
間主観性の定義は、「意図的に希求される、出来事と物事に関する体験の共有(文献1)」です。すなわち、他人の経験を自分の中で体験する事を示します。スターン(文献2、理論編p.150~156)によれば、間主観性とは、注意の的を共有する事、意図の共有、情動状態の共有を含みます。注意の的を共有する事とは、例えば、母親が指差す方向を子供が見つめる行為等を指します。この時、母親と子供は同じ対象に注目しています。意図の共有とは、乳児がミルクを欲しがって泣いている時に、母親が即座にその意味を理解しミルクを飲ませる行為等を示します。最後の情動状態の共有とは、だれかが悲しくなって泣いている時に自分も悲しくなってしまうような状態を示します。すなわち間主観性の共有とは、他人の注意、意図、情動をあたかも自分の経験であるかの様に感じる状態を指します。こうした間主観性の共有が可能になるのは、生後7~9ヶ月からといわれて(文献2、理論編p.146)、間主観性を共有する能力はその後も維持されます。
セラピーのセッションの中では、セラピストとクライアントの間にしばしば間主観的な関係が生じます。セラピストがクライアントのこころの葛藤を理解しようとするうちに、セラピストとクライアントの間には、その内的世界を共有する様な共生期(文献3)の乳児の母親との関係に近い状態になる場合があります。共生期とは、生後6ヶ月程度から始まる、母親と子供があたかもひとつの自我を共有する様に見える状態で、母親は、子供の感情や欲求を自分のものであるかの様に理解する事ができます。クライアントと間主観的な関係が生じている時、セラピストは、共生期の乳児の母親と同じ様にクライアントの感情を自分の体験として感じるのです。例えば、いらいらしているクライアントの前では、セラピストもいらいらした気持ちを感じたりします。また、クライアントの内的世界が、セラピストの身体的な感覚として伝わってくる事もあります。クライアントが怒りを感じている時、セラピストの腕の筋肉が堅くなったり、肩がこってきたりする事もあります。
セラピストのバーバラ・ホリフィールドは、間主観性の身体感覚的な共有の事例として、解離性健忘症の女性とのセッションの中で経験した突然の眠気について、彼女の論文の中で記述しています(文献4)。彼女のクライアント、ドロシーは、有能な58歳のエンジニアでしたが、長年不安やパニックに襲われたり、記憶が部分的に無くなってしまう解離性健忘の症状に悩んでいました。ホリフィールドがセッション中で突然の眠気に襲われたのは、彼女がクライアントの解離性の症状についてワークしている時でした。セッションを続けて行くうちに、この眠気はクライアントと間主観的な感覚を共有している事による事が明らかになってきました。クライアントは、子供の頃家族から肉体的・性的・心理的な虐待を受けてきました。彼女は、自分自身あるいは彼女の姉が虐待を受けている時、あらゆる感覚から自分を切り離し眠ってしまおうと試みる事で自己を防衛してきました。ホリフィールドが感じた眠気は、クライアントの防衛機制を共有したものだったのです。セッション中の眠気の意味を理解する事により、彼女は、クライアントのトラウマを共感的に理解する事ができました。
この様に、セラピストとクライアントの間の間主観性の共有は、共感を導き、その結果セラピーのプロセスを推し進める要素となり得ます。セラピストの共感は、クライアントにとって間主観的に体験されます。こうした体験により、クライアントは自分が癒される価値のある人間である事を知り、自分のこころの傷を抑圧するのではなく対面する勇気を持ちます。このためには、セラピストは非防衛的で、純粋性を保ち、逆転移に対し敏感でなければならず、セッションの中で、セラピストの中になんらかの感情の動きがあった時、それは自分の固有の感情なのかそれともクライアントの感情を間主観的に感じているのかを見極める様努力しなければなりません。自分の固有の感情を、間主観的な感情の共有と勘違いすると、クライアントをセラピストにとって都合のいいように導いてしまう危険性があります。また、逆に間主観的な感情の共有を自分の固有の感情と勘違いしてしまうと、クライアントに対する共感は生まれません。間主観性は、セラピーの有効な要素になり得る反面、その扱いを間違えると、セラピストがクライアントが慣れ親しんだ破壊的な対人関係のシナリオを再演するような形で無意識に働く(文献5、p.212)事にもなりかねず、そうした場合、逆にセラピーの大きな障害にもなり得ます。
間主観性の概念は、伝統的な精神分析のアプローチであるブランクスクリーン、すなわちセラピストは、逆転移を防ぐために自分の感情は表明しない手法に疑問を投げかける結果となりました。間主観性の概念に従えば、セラピストは完全に客観的にはなりえず、また、セラピストが純粋性を保っていれば、セラピストとクライアントの相互の関係の中で、セラピストの逆転移が建設的な形で利用され得るからです。従って、心理力動的なセラピーの現場が、より自己開示していく方法や逆転移を開示する方向へと動きはじめています(文献5)。しかし、逆転移感情の開示は、前述した様に使い方によっては、セラピーのプロセスに悪影響を及ぼします。セラピストは、「セラピーは、クライアントの利益のためのものである」事を十分に認識し、セラピーの現場における行為について、常に「この選択をクライアントのために行っているのか、それとも自分の欲求を満たすために行っているのか」自問していかなければなりません。
(文献1)Trevarthan, C. & Hubley, P. (1978). Secondary inter-subjectivity: Confidence, confiders and acts of meaning in the first year. In A. Lock (Ed.), Action, gesture and symbol. NY: Academic Press. (文献2)スターン、D.N.「乳児の対人世界」、岩崎学術出版.(文献3)マーラー、M.「乳幼児の心理的誕生」、黎明書房(文献4)Holifield, B. (1998), Against The Wall / Her Beating Heart: Working With The Somatic Aspects of Transference, Countertransference, and Dissociation, Inquiries in Somatic Psychology (Body in Psychotherapy, Vol 3), by Don Hanlon Johnson (Editor), Ian Grand (Editor) North Atlantic Books(文献5)カーン、M.「セラピストとクライエント」、誠信書房